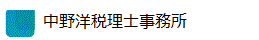税務だより
消費課税と人件費

消費税の税率が平成29年4月から10%に引き上げられることになっています。この消費税は、別名、付加価値税とも呼ばれます。この付加価値とは、大まかにいえば、売上高から変動費(商品・原材料費など仕入れに相当するもの)を控除したもので、人件費を控除する前の
金額です。そのため、売上原価の中に人件費などが含まれる製造業などでは、売上総利益(いわゆる粗利)は、付加価値とはいえません。付加価値は、労働コスト(人件費等)と資本コスト(設備投資等)から形成されるからです。
付加価値(消費)に対する課税とは
わが国の消費税は、取引時に売上に上乗せされ、製造→卸売→小売→消費者といった経済活動の取引連鎖の中で転嫁される税であり、最終的には消費者が税を負担する仕組みとなっています。つまり、消費税は多段階課税方式で、事業者が自らの事業活動で生じた付加価値に対する税金を、それぞれ納付する制度です。各取引段階で納める消費税は、各事業者が、売上に上乗せした消費税から、仕入等に含まれる消費税を控除して、その差額を、国に納付します。
所得課税(法人税・所得税)における課税ベースは、収益からコスト(原価・費用・損失)を控除したもので、人件費もコストとして控除されます。他方、消費税の課税ベースでは、付加価値を得るために要した人件費が控除されません。さらに、資本コスト(設備投資・諸経費)については大体が控除されますが、金融費用(支払利子・保険料)等についても控除されません。
例えば、1,000円で原材料を仕入れて、500円の人件費を払って、2,000円で売ったとします。このとき、付加価値は1,000円で、利益は500円です。前者は、消費課税の課税ベースとなり、後者は、所得課税(法人税・所得税)の課税ベースとなります。つまり、商売に対する利益は500円しか残っていないのに、仕入れた財貨に対して1,000円の付加価値が産み出されたとして、これに課税するというものです。さらに、上記の例において、労働生産性が低く、1,000円の人件費を要したとします。この場合、利益はゼロで所得課税は免除されるのに対して、付加価値が1,000円生じたとして、消費税が課されることになります。
単純化していえば、消費課税は、主に人件費に対して課税する仕組み、ということもできるでしょう。反面、所得課税は、事業活動で生じたすべてコストが控除されます。しかし、企業の業績の低迷により、所得課税の税収が減少しています。そこで、国は財源確保の手段として、より広い課税ベースである消費課税により財源を確保することになります。
消費税率アップの影響は

ここで、消費税は間接税であり、最終消費者が負担するものであるから、企業や個人事業主が負担すると考えるのは間違っている、という指摘があるかもしれません。しかし、残念ながらその見方は外しています。
消費税が各取引段階で完全に転嫁できればもっともなご指摘でしょう。しかし、流通段階での競争が激化している中では、価格競争力の低い企業は、競合他社との比較において、或いは、相手と力関係において、消費税相当額を売上に転嫁できず、消費税相当額を自らの損益の中で負担せざるを得ないと考えられます。さらに、事業活動に投入する労働コスト等は、売上に対する消費税から控除できず、人件費等の費用が大きいほど、差額として事業者が納付する消費税が増加するからです。
消費税は、建前は、各取引段階で転嫁される税であり、取引価格に上乗せされるものです。しかし、実際には、取引価格は各取引当事者間の力関係によって決まることが多いと思います。この点については、インボイス方式を採用すべきとする考え方や、消費税相当額を転嫁させない事業者に対して、罰則を科す方向で是正すべきとする考えもあります。しかし、結局は、消費税の増加分を何らかの形で還元する事業者は売上を伸ばし、そうした余力のない事業者には取引が敬遠されることになるでしょう。
さらに、医療機関などに対して財貨・サービスを提供している事業者も深刻です。事業者が納付すべき消費税の計算上、仕入時の消費税は、売上に対応させて控除するからです。医療行為には、売上に対して消費税が課されないことから、仕入時に支払った消費税も控除できないのです。そのような事業者は消費税率のアップが自動的に仕入コストの増加となり、経営の圧迫要因になります。この点については、わが国の消費税がインボイス方式を採用していないことも影響しています。そこで、消費税が課されない事業を営んでいる事業者に対して、財貨・サービスを提供している事業者は、消費税率の増加分を売上に転嫁することができないことも考えられます。
近年においては、小売業の大規模化・量販店の台頭により、流通商品の価格決定力が小売業者に移り、これらの大規模小売店や量販店においても価格競争が激化しています。そして、小売段階における過当競争は、卸売・製造に対する取引価格の減少圧力となり、各取引段階における売上の下落要因となります。そして、売上高の減少→付加価値の減少→人件費の減少→家計支出の減少→売上高の減少、というデフレ・スパイラルにより経済全体の付加価値が減少し続けていると考えられます。また、GDPは一定期間に国内で産み出された付加価値の総和であるとされています。名目GDPは、日本国内で産みだされた生産物やサービスの付加価値の金額の総和であり、企業や個人事業者の付加価値の総和と密接に関係しています。わが国では、将来、人口の急激な減少により、付加価値の減少が予想されます。このことは、付加価値に対して課税する消費税の課税ベースが減少することを意味します。課税ベースの減少をカバーするためには、今後、さらなる消費税率のアップが必要となるでしょう。
まとめ
労働コストには消費税が転嫁されません。他方、資本コストには消費税が転嫁されています。資本コストは、概ね消費税込みで支払いますが、労働コストも、実は、消費税分を上乗せして考えないといけないのです。つまり、目には見えない債務、ということになります。しかし、支払時には見えていなくても、決算で消費税を計算する際に突如として現れます。人件費の支払いには、決算時に消費税の支払いがついてくる、と考えるべきでしょう。換言すれば、人への投資は付加価値とされ、消費税の課税ベースとなる、ということができます。そのため、今まで以上に労働生産性を上げることが必要となります。そのように考えると、労働コストは、外注費や人材遣費としてアウトソーシング化することが考えられます。さらに、業種等によっては、労働生産性の向上より、むしろ、資本生産性の向上により、付加価値を増加させようとするでしょう。
今後、商売の仕組みは、『人件費が消費税の課税ベースとなる』ことを踏まえて構築すべきでしょう。消費税が課されない非課税事業を行う事業者では、人件費が消費税の課税ベースとなりません。そもそも消費税を納付する必要がないからです。このことは、逆に、資本コストに転嫁された消費税が控除されずに、自らの損益コストとなることを意味します。これに対して、消費税が課税される事業者では、人件費の多寡が消費税の課税ベースに直結します。消費税率の上昇は、企業の競争力の優劣を、制度面から決定的にすると考えられます。価格競争力のない企業は、消費税の増加分を売上に転嫁できず、自らの損益の中で負担することになるからです。卸売業などの売上総利益率(≒付加価値率)が10%前後とされる業種にとっては、消費税が転嫁できないと商売が成り立ちません。国の財源確保の手段として見直された消費税率ですが、まさに、天の声によって、どうにもならなくなり、撤退せざるを得ない企業も出てくるでしょう。
最後に、元々、所得課税の世界では、人の能力は課税ベースとなりません。より優れた社内体制を構築したとしても、その社内体制には課税されません。しかし、消費税(付加価値税)率の大幅な上昇が見込まれる今後は、課税ベースを考える上で、より重要な要素となります。つまり、社員のスキルや社内体制は、価格競争力の優劣にも繋がりますが、消費税の課税ベースにも大きな差異を生じさせるからです。労働生産性が低く、粗雑な社内体制では、労働コストがかさみます。そのことにより会社の業績が悪化しても、消費税の負担は減りません。それどころか、競合他社との価格競争の中では、労働コストに対する消費税を売上に転嫁できず、さらなる業績悪化を招きます。今はまさに、消費税の大増税に備えて、商売の仕組みを根本から見直すべき時期ではないでしょうか。