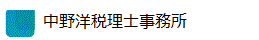個人のお客様へ-相続税
相続税対策
相続対策とは

相続税料金表はこちら→ 相続税料金表
相続税では、財産の多寡に応じて累進税が課されることから、課税対象となる財産の価額によって税負担が異なります。そこで、相続対策では将来の課税財産の価額を下げて相続時の適用税率を下げることや免税点(基礎控除)以下とすることがメインとなります。その方策としては、生前贈与や譲渡(売却)のほかに、相続財産の評価額を下げる評価減対策があります。
生前贈与による相続対策
生前贈与については、相続開始前3年以内に法定相続人に対して行われた贈与は、相続財産に加算されることになっています(相続発生直前に相続財産を贈与することによる租税回避を防止するため)。このことは、逆に、法定相続人以外に対する贈与については、3年以内の贈与であっても相続財産に加算されないことを意味します。例えば、孫に対する贈与(養子縁組をしていない場合)については、相続開始直前の贈与であっても相続財産に加算されないということです。
また、制度として贈与税が非課税とされている以下の3つの贈与については、法定相続人に対する贈与であっても、さらに、相続発生直前の贈与であっても相続財産に加算されません。但し、相続発生直前の贈与については、被相続人の意思能力等を踏まえ、贈与が真正に成立したことを証明できるようにしておくべきです。
①夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの贈与税の非課税
②父母や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
③父母や祖父母からの教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
・ 相続時精算課税制度の活用法
相続時精算課税制度は、65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子に対して(平成27年以降は、贈与を受ける者に推定相続人以外の孫が追加され、贈与をする親などの年齢も60歳以上に引下げられます)、最高2,500万円までの生前贈与を非課税とする制度です。よくある質問として、生前贈与と相続時精算課税制度は、どちらが得か?ということを聞かれます。この制度の最大のメリットは、親の意思判断能力がしっかりしているうちに、相続発生時の遺産分割協議を待たずに、まとまった額の財産移転を実現できることです。但し、相続発生時には、残った相続財産に加算して、相続税申告書を提出して精算する必要があります。よって、親の財産が相続税の免税点以下である場合には、財産の早期移転の観点から、非常に有効な手段となるでしょう。また、受贈者毎に2,500万円を超える部分に対しては、20%の税率で贈与税が課されることから、一般的に、財産が多い方は、先ず、生前贈与を計画的に行う方が有利といえます。
譲渡(売却)による相続対策
・ 土地の移転と一物四価
土地等の価額については一物四価が併存しています。税法では実勢価額・公示価額・路線価評価額・固定資産税評価額の複数の公定評価額を斟酌していますが、贈与や相続で使用される価額は、路線価による評価額です。しかし、親族間の相続・贈与で使用される路線価評価額と市場取引で現実に成立する価額(実勢価額)の間には、乖離があります。さらに、実勢価額については、簡便的に、路線価評価額を80%で割戻すことも認められています。つまり、税法では、時価を一義的に定義していません。そこで、これらの歪を利用した裁定取引が生じる余地が存在します。例えば、土地の市場価額(時価)が相続税評価額より高い場合、これを親族に贈与した上で、譲受けた親族が、当該土地を時価で譲渡すれば、差額部分は親族の利益となります。逆に、利用価値の低い土地や節税効果のない土地等であれば、早めに第三者への譲渡を検討すべきでしょう。
・ 財産の移転と課税方法
土地・建物の譲渡による所得は、他の所得との損益通算や損失の繰越しができませんが、同一所得の範囲内では通算できます。よって、同一年度内に含み益資産と含み損資産を譲渡すれば、譲渡所得税の負担を軽減することができます。また、不動産の譲渡による所得には、比例税率が適用されます。他方、相続税には累進税率が適用されます。よって、多くの資産を保有する資産家の方には、行く行く高い累進税率が適用されることになります。この点を踏まえると、事前に不動産を譲渡すれば、当該不動産の移転については、低い税率が適用される上に、残った相続財産の税率適用区分を下げる効果も期待できます。

但し、税効果を試算する場合には、流通税(登録免許税・不動産取得)や仲介手数料をも加味した上で行うことになります。さらに、親族等への譲渡の場合、譲受人に資力が必要なことから、総合的な検討が必要となります。
寄附による相続対策
・ 遺産分割協議の重要性
不動産の相続があった場合、基本的には、相続が発生した時点の法定相続人間で、遺産分割協議書を作成し、不動産を誰が相続したかを登記します。この時、今は使わないからと相続登記をせず、放置しておくことがあります。しかし、相続登記をしないまま放置しておけば、その相続人の次の世代は勿論、延々と問題を生じさせる可能性があります。つまり、そのままでは、土地を処分できないにもかかわらず、未分割の財産に対する法定相続分は、次の相続でも相続財産となり、放置している期間も固定資産税の負担が生じるからです。しかも、先々、不動産を処分する際には、結局、法定相続人間で作成した遺産分割協議書が必要になります。相続発生時から期間が経つと、相続人間の関係が疎遠になったり、関係が悪化していることがあります。そうなると、協議がまとまらず、遺産分割協議書に署名・捺印をしてもらい難くなります。さらに、当時の法定相続人が亡くなり、子の世代、孫の世代が法定相続人になれば、知らない者同士で、ますます遺産分割協議が成立し難くくなります。未分割のままでは、不動産を売却することができません。そして、売却に反対する法定相続人がいる場合も、不動産を売却することができません。従って、未分割の状態で放置するのは勿論のこと、共有名義で遺産分割をするのも、好ましいことではありません。
・ 非課税財産となる国等への寄附
前述のとおり、放置している相続財産からは、何の利益ももたらされませんが、未分割財産に対する法定相続分は、次の世代の相続でも、相続財産となります。むしろ、子や孫の世代では、相続財産としての認識がないことから、無申告となり、それを税務調査等で指摘されるリスクが生じます(但し、基礎控除以上の相続財産の場合)。そうなると、処分したくても、処分できない不良資産と化す可能性があります。不良財産という問題を後世に残す結果とならないよう、最初の相続発生時には、全力を注いで問題の芽を摘んでおくべきです。従って、誰も使わない土地は、国等に寄附をして相続税の課税対象から外すことも検討すべきでしょう。寄附は、社会貢献の目的で行われるものです。従って、非課税となる寄附は、国や地方公共団体及び特定の公益法人等に対するものに限定されています。しかし、将来、使用する見込みがなく、かつ、売却したくても売却ができない財産については、これらの相手先に寄附することで、相続税の負担を軽減すべきでしょう。例えば、山林などの遊休土地以外にも、書画・骨董品や美術品などがこれに該当します。 寄附による相続対策には、①生前の寄附と②相続発生後の寄附があります。②の場合は、相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していることが前提となります。従って、被相続人の意思により、事前に生前の寄附を行う方が望ましいといえるでしょう。
不動産の評価減による相続対策
最後に、最も重要で、第一に検討すべきなのが、評価減対策です。評価減対策としては、多くの場合、自宅敷地に対する特例適用の可否がポイントとなります。この特例は、一言でいえば、自宅の土地であれば一定の面積までは80%の減額をすることができ、3,000万円の土地も600万円で計算して良い制度、ということです。主な相続財産が自宅の方は、この制度を適用することができれば、相続税対策がほとんど済んだといえるでしょう。しかし、この制度は誰でも適用できるものではありません。一定の要件を満たさなければ適用することができません。そのため、この制度が適用できるか否かを事前に確認しておくことが重要となります。
・ 収益物件の購入・建築
資産家の方の有効な評価減対策として、収益物件の購入・建築という方法があります。収益不動産の評価では、賃貸に供している土地や家屋について、その権利関係に応じた評価減を受けることができるからです。建物は、固定資産税評価額で評価しますが、その評価額は、一般的に標準的な建築費用の70%程度で評価されるようになっています。そして、賃貸に供している建物については、さらに借家権割合(30%)の評価減を受けることができるため、建物の評価額は、70%×(1-30%)≒50%ということになります。その結果、5,000万円で収益物件を建築しても、2,500万円の評価額となります。そして、これを借入で賄った場合、2,500万円-5,000万円=▲2,500万円となり、全体として相続財産を2,500万円減らす効果が生じます。しかし、事実上、賃貸に供していない部分(空室割合)については、借家権割合を控除できないことから、自用家屋の評価になります。土地についても、その上に賃貸不動産があるということで、『貸家建付地』として約20%程度(1-借地権割合×借家権割合)の評価減を受けることができます。但し、この場合も、賃貸に供していない部分の評価が自用地評価となります。以後は、賃料収入から借入元金と利息等を控除した部分が、家主の現金収入となります。

但し、投資利回りの判断や物件を誰が相続するか、など先々のことを考えておくべきです。そもそも不動産投資に興味がない場合、不動産の維持・管理がおろそかになり、不良資産と化す例もあります。
納税資金対策
収益物件の購入や建築は、賃料収入による財産形成が見込まれることから、納税資金を確保するためにも有効です。しかし、収益物件に対する借入金の負担や不動産市況の影響を考慮する必要があります。物件の需要が薄れた場合、維持・メンテナンス費用と借入金の負担が重くのしかかるからです。不良資産を残すことにならないよう、慎重な投資判断が必要です。とはいっても、遊休土地を多く所有しておられる方などは、やはり、検討すべきです。例えば、総財産のうちに不動産が占める割合が多い方は、納税資金の捻出が重要課題となるからです。また、多額の不動産評価額に対して、現預金が少ないケースでは、最終的に不動産等の物納を検討することになりますが、ハードルが非常に高いので注意が必要です。すなわち、物納を申請する場合、不動産の権利関係を明確にする等、いつでも換金できる状態にしておかなければならない上に、当該制度は、延納(分割払い)によっても金銭で納付することが困難な状況にあり、かつ、その納付を困難とする金額を限度として認められているに過ぎないからです。物納が認められなかった場合、不動産を税務署に担保に取られた上で、延納(最長20年の分割納付)となります。この場合、延納に対する利息も課されます。
また、納税資金対策を考える場合、生命保険金の活用を検討すべきです。つまり、各相続人毎に予測される相続税を試算した上で、それを保険金でカバーするのです。被保険者と保険料負担者が被相続人であり、かつ、死亡保険金の受取人が相続人である生命保険金については、一定の非課税枠があり、その非課税の枠内の保険金は、全額が納税資金の原資となります。この場合、終身保険を活用するのが良いでしょう。納税資金の確保を第一に考える場合、相続発生まで契約が継続していることが必要であり、それまでに満期が来ては意味がないからです。さらに、長生きすればする程、保険料の負担が年々増す終身払込みの保険契約は避け、一時払い又は有期払込にすべきです。また、納税資金の確保を目的とするため、解約返戻金を考える必要がありません。そのため、できるだけ保険料の安い低解約返戻金型の終身保険や最低保証額が確保された変額終身保険を活用すべきでしょう。
生命保険(民法上の扱いを受けた留意点)
・ 争族と生命保険
生命保険金の受取りは、民法上、被相続人の財産とはならず、受取人固有の財産となります。そのため、被相続人が負担した保険料によって受取った保険金であっても、相続人間の遺産分割協議の対象にならず、さらに、遺留分減殺請求の対象にもなりません。そのため、相続人の受取った保険金は、遺産分割協議の法定相続分からも、遺留分の計算においても、除外できるのです。よって、相続に争いがある場合、受取った保険金については、遺留分を請求される側でも、遺留分を請求する側でも、貰っていないものとして計算することができるので、まるもうけです。つまり、保険は”争族”においては、もろ刃の剣となります。しかし、いずれに有利に働くか(誰を受取人にするか)は、保険契約者の意思によります。
・ 代償分割資金としての生命保険
生命保険金は、遺産分割における代償分割資金としても有効です。例えば、相続人に長男と次男がいて、相続財産が主に自宅不動産である場合、基本的に不動産は共有名義で相続すべきではありません。そこで、長男が不動産を取得する代わりに、次男には生命保険金を原資とした代償金を交付するのです。この場合、不動産を取得する予定の長男を保険金の受取人とするのがポイントです。万が一、遺産分割で争いが生じた場合、生命保険金が遺産分割の対象にも、遺留分の対象にもならないことから、次男が生命保険金を受取ったとしても、別途、代償金を請求するかもしれないからです。また、長男に資金がない場合、被相続人が保険料を負担する配慮も時には必要でしょう。つまり、①親が保険料相当額の現金を長男に贈与し、②親を被保険者とする保険契約を締結し、③長男を保険金の受取人とするのです。この場合、年間の保険料が贈与税の基礎控除額(110万円)を超えれば贈与税の申告をする等、贈与の事実を証明できるようにしておくべきです。
・ 相続放棄と生命保険
被相続人が、事業で多額の借金を抱えていたり、借金の保証人になっていたりする場合、相続人は、相続の放棄を考える必要があります。つまり、相続があった日から3ヶ月以内に相続の放棄をしないと、被相続人の借財を承継することになるからです。この場合、被相続人の負債の弁済義務が相続人の固有財産にも及びます。そのため、相続人を受取人とする生命保険金であっても、被相続人の借金の返済に充てられることになります。しかし、相続を放棄すれば、被相続人から受取った生命保険金は、借金の返済に充てる必要がありません。これは、生命保険金が民法上の相続財産ではないからです。
・ お早目のご相談を

上記でご紹介した相続税対策は、ほんの一例です。オーナー会社の株式評価減対策や複数の不動産や金融資産を保有しておられる方、事業を営んでおられる方などは、事前の対策が必要・不可欠です。お早目のご相談をお待ちしております。