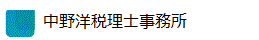経営だより
労働分配率と労働生産性

リーマンショック以降の経済環境の激変から2008年9月を境に企業の業績が急激に落ち込んでいます。当時の3月決算法人の業績をみると経済環境が様変わりしているため、上半期と下半期で業績に極端な違いがみられました。
つまり、上半期の黒字を下半期の赤字で食い潰し、一年間を通じた分析結果には何の意味もなく、翌期の見通しは赤字の一途を辿るというものです。そのような状況下で、やみくもにリストラ等による人件費の調整を進めている状況もみられました。
このような時には、適切な経営分析ができないと、適切な経営判断ができません。リストラ等により、いくら人件費を抑えても、企業の人件費負担は重いままで、労働分配率はすぐに上昇します。これは、企業の付加価値の減少が止まらないからです。つまり、企業の売上高が減少→付加価値の減少→人件費の減少、というサイクルから家計の収入が減り、それが購買力の低下を招き、また売上高が減少する、という負のサイクルが延々と続いていると考えられます。そこで、企業の付加価値と人件費の関係を考えてみます。
経営分析に欠かせない重要な指標に、労働分配率と労働生産性があります。これらの指標は、いずれも付加価値と労働力の関係を示すものです。両者は、相互に連動して考えるべき指標であり、従業員の給与水準が妥当かどうかを、労働効率から判断することができます。
労働分配率(付加価値に占める人件費の割合)
・労働分配率=人件費/付加価値 ※付加価値=(売上高-変動費)
上記の算式から、売上高が減少し付加価値が減少すれば、人件費が増加しなくても、労働分配率が高くなることが判ります。と同時に、それが経営のマイナス要因となることから、人件費を調整する方向に働くことも読み取れます。
人件費の水準を計る労働分配率については、何を基準とするのか、どの年度の数値が望ましいのか、という点について明確な指針をもっていない会社が多いように感じます。経済環境が目まぐるしく変化する今日においては見失いがちです。結論からいいますと、労働分配率は、高くすべきものでも、低くすべきものでもなく、その会社ごとに、『あるべき一定の水準で推移しているかどうかを管理すべきもの』でしょう。儲かったからといって、労働分配率を高くし過ぎると、内部留保が満たされず、以後の設備投資等にも影響が出ます。逆に、赤字であるからといって、いたずらに人件費をカットして労働分配率を下げると、従業員の労働意欲の低下に繋がります。会社としては、従業員に労働分配率の指標を示して、現在の給与水準が妥当な水準にあるかどうかを示すべきです。その上で、労働分配率が適正水準よりも高いのであれば、目標水準の分配率に到達するまで一丸となって仕事の効率(=労働生産性)を上げるようにすべきですし、逆に、適正水準より低いのであれば、適正水準までの成果を従業員に還元すべき場合もあるでしょう。
そこで、先ず、労働生産性を上げることを考えてみましょう。これは、人員配置を見直すことでも実現できます。例えば、社内の人員配置が、硬直的で部署毎に繁忙期を想定した(繁忙期に業務が滞らないような)ものとなっている場合には効果的です。この場合には、社内業務をマニュアル化することで、複数の人員が複数の部署を兼任できるようにするのです。一般的に、部署毎の繁忙期は異なるものです。社内の応援体制を整備することで部署毎の業務に要する人員数を平準化すると、急な欠員による業務の滞りを回避しながら人員を整理し、全体として『労働生産性を上げ、労働分配率を下げる』ことができます。
また、人件費を変動費化したり、別枠の固定費とすることでも、労働分配率を下げることができます。例えば、正社員が行っている業務を非正規社員や外注先が行うようにし、さらに、新規雇用を抑えて、その分の業務を既存社員の残業手当で賄っても、人件費を抑えて、これを変動費化することができます。このように、労働分配率は労働生産性と密接な関係をもっています。というより、両者は表裏一体の関係にあるといえます。それは、次の算式からも明らかです。
労働生産性(従業員一人当たりが産み出す付加価値)
・労働生産性=付加価値/従業員数 ※付加価値=(売上高-変動費)
上記の算式から、付加価値が増加したり、従業員数が減少すると、労働生産性が高くなることが判ります。そのため、売上高の増加や変動費の減少により付加価値が増加し、一人当たりの労働効率が向上すると、給与として労働分配率に反映させるべきと考えられます。しかし、この労働生産性は、トレードオフの関係にある資本生産性(資本生産性 = 付加価値 ÷ 固定資産)の影響を受けます。例えば、製造業などでは、労働コスト以外にも多額の資本コスト(固定資産等)が投入される分、労働生産性が高く(反面、資本生産性が低く)なる傾向にあるのです。これは、付加価値が資本と労働から産み出されることを示すものです。そのため、付加価値が増加して労働生産性が向上したからといって、それは労働効率の改善によるものではなく、資本コストからもたらされるものかもしれないのです。つまり、付加価値の増加要因が、設備投資(資本コスト)によるときは、むやみに労働分配率を上げるべきではないと考えられます。このような設備投資が他人資本によって賄われている場合、その返済額(借入元本+支払利息)が付加価値の増加に貢献していると考えて、これを加味した上で労働分配率を管理すべきかもしれません。また、設備投資がリースによって賄われている場合、リース費用部分が付加価値の増加をもたらしていることも考えられ、これを考慮することになるでしょう。
まとめ
このように、労働分配率や労働生産性は、やみくもに他社と比較すべきものではありません。労働分配率と労働生産性は綱引きの関係にあるため、基本的には、労働生産性が向上すれば、労働分配率を上げる方向で検討すべきです。しかし、資本生産性の影響も考慮すべきであり、付加価値の増減要因を分析することが必要です。その上で、労働分配率が適正な範囲で推移するように管理すべきであり、会社によってその基準値やアローワンスは千差万別です。
会社の業績が悪化したからといって、むやみに人員整理をすればよいというものではなく、まず、付加価値を増加させる努力をすべきで、それでも立ち行かなくなった場合、不採算の事業部門を整理し、その事業に携わる人員の整理をすることになるでしょう。しかし、口で言うのはたやすいことですが、実際は簡単ではありません。注意点の一つとして、人件費の減少→売上高の減少→資金繰りのへの影響、というサイクルを考える必要があります。リストラ局面では、得意先ごとや事業部門ごとの採算性を把握し、撤退費用や資金繰りへの影響を折り込んだ上で、資金繰り予算を立てる必要があるからです。例えば、収益性が低い得意先であっても大口得意先の場合、資金の回収サイトが早ければ、撤退後の資金繰りへの影響が大きいので注意が必要です。
労働分配率や労働生産性に関する経営指数を重点管理項目とするのであれば、人件費等を管理するための経理の仕組みを整えた上で、そこに焦点を当てた経営分析が継続的に行えるようにしなければなりません。社内の業務改革を必死に行って、労働生産性が上がっているはずなのに、それが経営数値として分析されていなければ、従業員の努力が労働分配率に還元されません。そうなると、従業員のモチベーションはますます下がり、会社の業績にも跳ね返ります。つまり、指針となる経営数値を『見える化』しておかないと、経営の舵取りができないのです。そして、これらの経営数値の分析を、会計ソフトから出力された推移表や経営分析表のみで行っても、甚だ不充分で殆ど役に立ちません。
しかし、すべての経営数値について精緻な分析を行う必要はありません。会社にとって重要な経営指標を管理すればよく、要するコストと得られる成果のバランスを考慮すべきです。会社によって、管理すべき主要な経営指標や依るべき経営指数は異なり、企業のニーズによって多種多様な経営分析のフォーマットが必要となります。そのような観点から、中野オフィスでは、お客様のニーズに合わせて経営分析のフォーマットを用意することにしました。